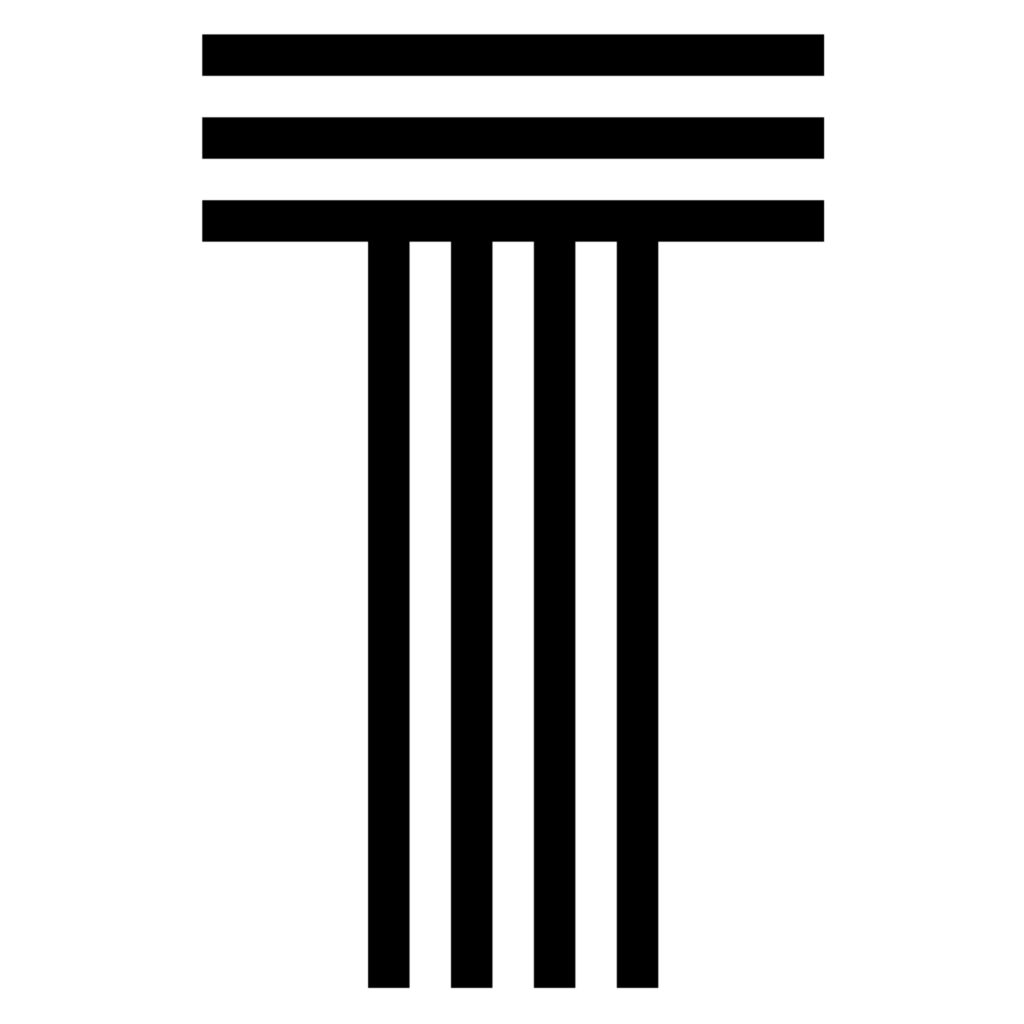第2回 バカの一つ覚え
すべてのきっかけ:落第
私が英語を勉強し始めたのは、中学生の時。そのきっかけは、とある定期試験でした。
もとから大して勉強もせず、平凡以下の学生だった私は、宿題も答えを丸写し。
試験前もろくに勉強せずに、英語読解の定期試験に臨みました。
しかし、世の中は甘くはありません。
70点がボーダーラインの試験で、私の点数は69点。
「あと一点足りていれば……」そう悔やみましたが、点数は点数です。
私はその試験を落としてしまい、みっちりと課題をさせられました。
誰にでもよくある話かもしれませんが、落第すると誰でもいい気分はしません。
痛い目を見た私は、それ以降、英語の授業に予習と復習をして臨むことにしました。
小さな努力が生んだ、小さな成果と大きな自信
当時の中学校の授業といえば、基本的な文章が書かれた英語の教科書がメイン。授業中は、一章ごとに教科書を読み進め、丁寧に解説していくスタイルです。
中学英語の教科書の文章は、基本的な文法や単語が凝縮された例文のあつまり。しっかりと読み込み、自分のものにしていく価値がある文たちでした。
その為、授業ごとに行われる小テストは、「教科書の文章をそのまま和訳したり、英語に戻す」だけ。
ですから私は、空き時間を見つけて、教科書の文章を音読し、ろくに意味も分からずにひたすら暗記をするという作業に没頭していました。
教科書の文章は短いので、十分丸暗記できる量でしたし、先生にもそうするように薦められていたからです。
そうして日々の小テストに臨むようになり、私の点数は一変。
それまでボロボロの点数だった小テストで、私は毎回満点を取れるようになりました。
短い教科書の文章そのままなのですから、暗記していればできるに決まっていますね。
点数が上がったとはいえ、英語が出来るようになったわけではありません。バカの一つ覚えをしただけです。
まったく大したことのないことですが、一つの変化が起きました。
それは、英語の先生の評価が変わったことです。
私はバカの一つ覚えでしたが、小テストの成績は毎回満点。先生も、「キミ、英語できるようになってきたね」という風に褒められるようになりました。
「全然なってねえわ」
と心の底で思いつつ、褒められて悪い気はしませんでした。
その後迎えた定期試験も、小テストと同様に教科書の文章ほぼそのまま。人の名前をすこし変えただけのような問題ばかりでした。
その為、意味もロクにわからず、教科書を全暗記して望んだだけの私は、突然にして成績トップに。
今考えると、周りの生徒もあまり勉強していなかったのでしょう。
何も理解出来ていなかったくせに、「自分は英語ができるんじゃないか?」と、謎の自信と錯覚が生まれ始めました。
「バカの一つ覚え」が成果を発揮
私がした、「バカの一つ覚え」。ロクに文法や意味も理解せず、ただひたすら音読して暗記していくスタイルです。
やっていることは確かに、バカそのものです。私が優秀な生徒であれば、きっちりと文法や単語を理解して、どんな文章や問題が出ても柔軟に対応するでしょう。私のようなバカの一つ覚えでは、到底かなわなかったかもしれません。
しかし環境も幸いし、丸暗記でもいい成績が取れるという、うまい汁を吸ってしまった私。味をしめ、他の英語の授業(読解だけでなく、文法の授業)でも例文暗記を始めました。
数学の試験では、丸暗記は通用せずに壊滅するのが関の山でしょう。
でも、英語の試験の場合は違いました。例文を暗記するだけだった私のスタイルが、他の英語の授業でも功を奏し始めたのです。
スポンサーリンク
「例文」はエッセンスの宝庫
先ほども言いましたが、中学英語の教科書や例文は、必要な単語や文法事項を盛り込んだエッセンスの宝庫。
それを自分のものにするだけで、基本的な力が身につくように、短い文章が緻密に作りこまれているのです。
先生が「教科書を丸暗記しろ」、と言っていたのもそのため。私はそれに、愚直なまでに従ったのです。
だからこそ、基本的な事項を問う中学の試験で、この勉強法は成果を発揮したのです。
「丸暗記」こそが、語学習得のすべての原動力
実は、この「丸暗記」。中学英語のみならず、あらゆる言語の習得の基礎にあるものということを、私は後々知りました。
考えてみてください。
赤ん坊の時、あなたは日本語を話すため、難解な文法事項を習ったり単語帳を必死で覚えたりしたでしょうか?
そうではないはずです。
お母さんやお父さんが話している言葉を毎日浴びているうちに、気が付けば当たり前のように言葉が出るようになっていた。
というのが普通でしょう。
こうして、実際に使われていることばをともかく飲み込み、自分のものにするというのは、言語習得においてとても大事になってくるのです。
第3回はこちら